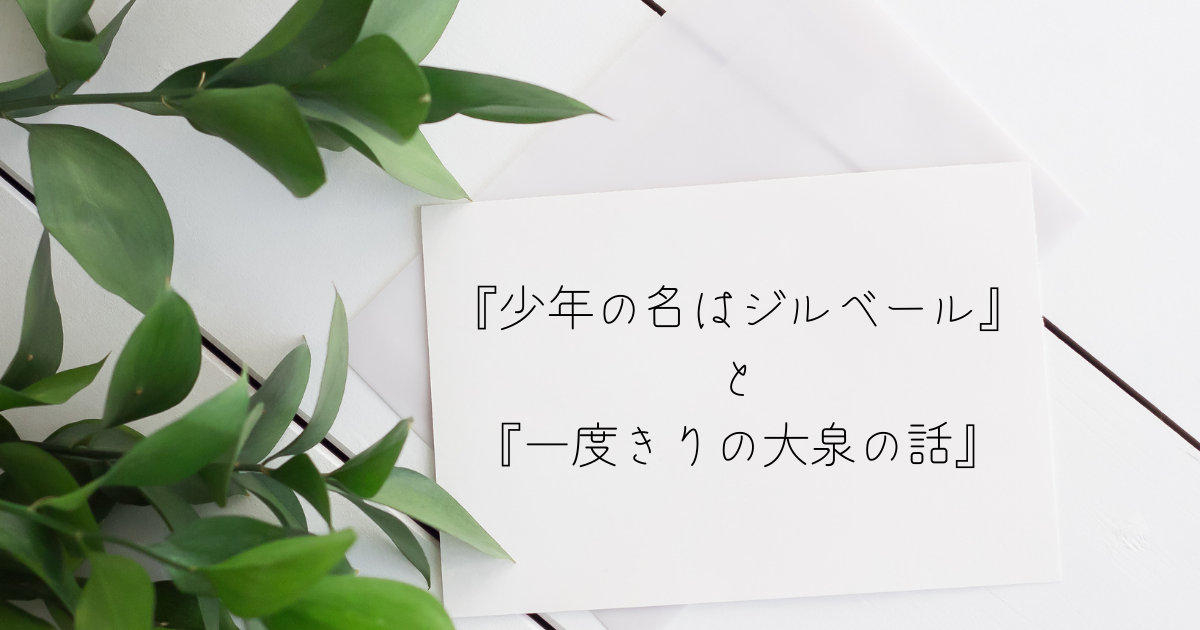
こんにちは。
萩尾望都さんと竹宮恵子さん。トップに君臨する漫画家として同時代を生き抜いて来たおふたりが、20歳ごろの2年間、一緒に住んでいたことは知りませんでした。深い確執があったとも知りませんでした。ですので、この二冊の存在を知り、いろいろと驚きました。
おふたりとも、現在70代。東京の大泉で一緒に暮らしその後距離を置くことになったのは、すでに50年前。ほぼ半世紀前のことになります。2016年に『少年の名はジルベール』が出版され、2021年『一度きりの大泉の話』が出版されました。その内容にファンは騒然となり、話題を呼んでいます。
竹宮恵子さんが『少年の名はジルベール』で萩尾さんのことに触れ、一緒に暮らした家が「ときわ荘」のように「大泉サロン」と呼ばれていたこと、萩尾さんの才能に嫉妬して解散したことなどを書いたため、以前からくすぶっていたゴシップ的な噂に火がついてしまいました。萩尾さんに問い合わせやドラマ化依頼などが殺到したため、萩尾さんがやむを得ず出したのが『一度きりの大泉の話』です。
確執のもとになる問題の出来事が、過去の心情的ないざこざであるのは間違いありません。しかしそれ以外のこと、当時おつきあいのあった漫画家さんやお友達との交流などがそれはもう活き活きと描かれていて、おふたりとも当時のことをまるで昨日のことのような鮮明さで語られています。そのことにまず驚きます。書き手が20代にしか思えなくなるような瞬間が、どちらの本にもありました。
正直「女あるある」な話だとは思います。女、というか、人の人生には、特に若い頃には、どんなに仲のよい友達でも、気持ちがすれ違って不和が生まれ、なんとなくであれ、大げんかの末であれ、離れてしまうことがあります。「女あるある」と先に申し上げましたが、男性と女性という分け方はこの時世穏当ではないかもしれません。でも小学校女子児童の「グループ」形成がきっかけのいじめなんかはよく聞く話ですし、事実、身に覚えのある女性も多いと思います。
それに加え、二人とも芸術家ですので「芸術家あるある」でもあると思いました。ゴッホとゴーギャンの例を取るまでもなく、一緒に暮らして破綻した芸術家同士は沢山います。互いの才能を尊敬しながらも相容れないのも、個性が際立てば際立つほどに溝は深いのも珍しい話ではないのだろうと推察されます。
竹宮さんはこの同居を始めるときに、ある編集者の方から「漫画家同士の同居は絶対やめた方がいい」と言われていたそうです。それでも強行した竹宮さん。竹宮さんと萩尾さんとの間には、もうひとり、増山さんという、彼女たちふたりに強い影響を与えた女性がいました。竹宮さんには、萩尾さんと共通の友達が当初からいたことで、多くの友人知人を招く「サロン」のようにして暮らしたいという目論見があったのかもしれません。実際、増山さんあっての竹宮さんと萩尾さんでした。
最初の頃は、九州と四国から出てきたばかりで、ふたりとも若く、性格の違いを感じても知人がいつも誰かしらいる環境だったためぶつかり合うこともなく、お互いに助け合って暮らしていたと思います。
二冊の本からは、ふたりが才能を認め合いながらも、互いに本音ではぶつかれない様子が見て取れます。おふたりとも相手を観察しながら「きっとこういう人なんだろう」「こんなふうに見えた」と、関係が推測や洞察で成り立っているように思えました。二冊の本を照らし合わせても、ふたりが心を割って率直に話をすることはほとんどなかったように思われます。竹宮さんは共通の志を持った増山さんとの関係を深め、萩尾さんは次第に孤立していきました。でもそれも、もともと話下手でマイペースな萩尾さんにとっては苦痛な環境ではなく、自分は自分の漫画を描ければいい、と思っていたようです。
萩尾さんは著書の中で「自分は空気が読めず、あとで失笑を買うタイプ」と書いています。でもそれは、萩尾さんが自己分析をしたものです。「親に叱責されて生きてきたので人の顔色をうかがう」とも書いており、増山さんと竹宮さんの関係には敏感だったはずです。ふたりの仲が親密に、深くなればなるほど、彼女たちと違う立ち位置を取る自分は、彼女たちから距離を置いておこう、外から見つめて居ようと思っていたように思われます。
実際に「一緒に時代をつくろう」と言い合ったのは、竹宮さんと増山さんだけであって、増山さんはのちに「あなたをひとりぼっちにした」と、萩尾さんに告げています。萩尾さんはおそらく最初から「一緒に少女漫画に革命をおこす」とか「同志」とは考えてみたことがなかったのでしょう。だから「サロン」だったとは思っていない、という言葉になるのだと思います。
ただ、自分の漫画を読んでもらうためには「読者」を意識しなければならなかったし、「ランキング」にも敏感でいなければならなかったはずです。ここに人が集まって喧々囂々話したことは、そこにいた誰もに時代の望むものを意識させ、「読んでもらうには人々の希望にこたえることだ」という空気が育ったことは間違いないと思います。竹宮さんと増山さんは「少年同士の同性愛」こそが自分の書きたいものであり、それを望んでいる人の希望に応えること、それこそが「少女漫画に革命を起こす」ことだと確信していました。実際、そうなったわけで、萩尾さんにも既存の概念を壊すような、新しい画期的な世界が「少年の同性愛」だという刷り込みが行われたとするならそれは「サロン」的だったのかもしれない、とも思います。少なくとも萩尾さんは「読者層はこういうものを求めている人が多いのだな」というムードを素直に受け取ったのだろうと思われます。
確かに私も、これまで萩尾さんも竹宮さんも少年の同性愛を描く人なんだと、漠然とひとくくりにしていました。作品としての完成度が高いので「そういう耽美な世界もあるよね」としか思っていませんでしたが、 ただ、竹宮さんの世界と、萩尾さんの世界は違うなとは思っていました。実際、萩尾さんは「少年の同性愛はぴんとこなかったが、主人公を少年にしてみたらその自由さに虜になった」といくつかのインタビューでも言っていました。
女の子は不自由だ、というのはよくわかります。以前は女性の人生に「恋をして結婚して家庭に入る」以外の選択肢がなく、そもそも「恋愛」すらできなかった時代が長かったので、とりあえず「恋愛」ののち「結婚」がゴール、が少女漫画の王道でした。『赤毛のアン』で男の子が欲しかったのに!というマリラのガッカリ感に傷ついたアンが、女性としてあらゆる幸せ(孤児だった少女が、家族、恋愛、結婚、仕事、家庭、子供を手に入れるお話)は相当、画期的だったと思います。だからこそ主人公を少年にするというアイディアはさらに画期的で素晴らしく、創作に携わる人を虜にしたのではと思われます。
自分の漫画が認められている実感もなく、試行錯誤を繰り返していた萩尾さんから見た竹宮さんは「先を行く、すでに活躍している先輩」であって同等のライバルとは思っていなかったようです。一方、竹宮さんは、着々と認められていく萩尾さんに自分の領域を侵されていく脅威を感じ、そしてその「少年の同性愛」に抱く感覚に根本的な差異を感じて、自分の作品をいかに周囲に認めてもらうかに焦りを感じていったようです。
追い上げて来る天才を見て、焦りもがき苦しむ竹宮さんの心情に共感する方も多いだろうと思いますし、その別れるに至った経緯には、萩尾さんに強く共感する方も多いと思います。
このとき起こった「決定的なこと」に関しては、ふたりの心の中にある「できごと」がそもそも、違っていたように思えます。
竹宮さんが『少年の名はジルベール』を書いたのは、「自分が築いた一時代、半生を語る」のがメインで、決して懺悔や、萩尾さんへの陳謝のためではなかったと思います(だとしたら逆に公の本には書けないでしょう)。もう半世紀も経つので時効、すべてはよい思い出、という気持ちだったのではないでしょうか。しかし萩尾さんは『一度きりの大泉の話』で「あのとき凍結した思いを再び解凍した」とおっしゃる通り、ものすごく生々しい感情を吐露しています。一見、萩尾さんのほうが強く固執しているように感じられますが、萩尾さんは「あの事件」と竹宮さんを排除して生きてきたからこそ「解凍」されたときの鮮度が強烈だったのであり、実は50年の間、ずっと相手が気になり続けたのは竹宮さんのほうだったのではないでしょうか。
同時代に生き、似たような活動の場で比較される天才は沢山います。前出のゴッホとゴーギャンは実際に同居していたことがありますし、ダヴィンチとミケランジェロ、項羽と劉邦、紫式部と清少納言、武田信玄と上杉謙信…キリがありません。確執があったライバル同士も数知れず。
しかし二人とも生きている間に、生々しい「すれ違い」の告白文を読む、というのはそれほどない経験です。読者のほとんどは、彼らの華々しい経歴と実績を目にして育ってきた世代だと思います。この2冊の本で読者は、憧れと尊敬を一身に集めている輝けるスターだったお二人の内面の懊悩に触れ、同じ人間として同情し共感し、そしてすれ違う繊細な感性と、火花が散るような魂のぶつかり合いを感じます。かなりドキドキします。
『冬の終わり』と言う松任谷由実さんの曲を思いだしてしまいました。
頑張るあなたが憎らしかったの
置いてきぼりにされるみたいで
傷つけた 迷ってた
同じだけ淋しかった
二人の周囲には、一緒に暮らしていた時も、別れた後も、たくさんの共通の友人知人がいました。彼女たちの一部始終を見ていた人たちがいました。赤裸々な話を語られなくても、親しかったらある程度、慮ることができます。その方々が、50年間、何もできなかったし、そっとしていたことです。この本が出ようと出まいと「これまでもこれからも、そっとしておこう」と思っていることでしょう。
彼らと親しい人々がそっと見守ってきたことに、読者がジャッジすることなどできません。おふたりが時代を牽引してきたことは紛れもない事実です。せめてこれからは、おふたかたともお心穏やかにすごされますように、と祈ります。